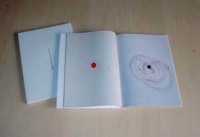
[未曾有の媒体にむかって]
平井亮一
2002 作品集[℃]
諸泉茂の仕事を積極的にみるようになったのは、1990年代なかば以降で、それも目盛りなしの温度計を機軸にした設営のオプティカルな訴求力にふれてからである。
何十本いや何百本かの温度計それぞれのガラス管を温度に応じて上下する赤い液体。それにガラス管の長短などなど。この素材と条件がいったん設定されるなら、原理上はそれだけでこれら物体と物質の装置としてのいわば自己発現は十全となろう。そのかわり設定のありようは当の素材の物性と機能に当初から規定されなければならない。そのかぎりでこうした物象と作為は潜在力の高い様相において、明確にみずからを指し示すだろう。そう、あの指示表出、それもそれじたいのありようを実現しそれをみずからさし出す自己指示。
図式になるけれど、すでに徹底した物質還元を経たのちの美術表出では、この還元ゆえにもはやしかるべき想念や事物の意味を充当する内包にはなりえない、という側面もあきらかになった。これを布衍するなら、そうした営為は世界や事物との接点でこの外延として機能するような表出実践であるほかない。とすれば方途としてこれはことがらの意味表現ではなく、多かれすくなかれことがらの指示たらざるをえないのである。問題はモダニズム/ポストモダニズムなどの流通概念でなく、そもそもの美術表出の存立にかかる原理上のことに属する。
むろんこのような理屈にたって諸泉が仕事を進めているというのではない。しかし、さきほどふれたかれの実践がもつ指示性について考えるなら、いまいつた表出パラダイムの変容事態は無視できない。そうでないとかれの営為はしかるべき意味を伝達するいわば象徴の柱、いや象徴の温度計として拡張解釈の海に投げこまれたまま漂ってゆくことになりかねないからである。
具体的にみてゆこう。かれの設営では温度計の長さ、様態、数、配列などは作家の裁量によるけれども、管のなかの液体と温度との相関で液体の膨張/収縮率はすでに一定である。そのうえでかれは環境温度の変化、それに微妙に関与する観客の体熱など偶然の作用因子にかぎられた最小限の条件下で出来するこれらの相互干渉をくっきりと可視化する。たとえば同一の管と液柱を垂直あるいは水平にすこしずらして並べる、また一定温度状態を液柱の同一水平位置に定め、管のサイズその他の条件次第で長さの異なる液柱を下方にのばすなど、物理的にも視覚的にも必要かつ最小限の差をあたえることで設営の規矩を演出している。物質的な条件のちがいに明確な秩序とかたちをあたえ、そのことの総体をひたすら同義反復的に指し示すのだ。そのいっぽうで、営為の反復拡張ないし原理的な無限反復の構造をしのばせることによるあるポジティヴな形式が創出されている。
そればかりか、お望みとあればかれは、回転する円盤上に管を放射状に並べて液柱に遠心力を関与させるかと思えば、ハート型の管を、赤い液柱のゆらぎで文字どおりウォームハーティッドにすることだってできるだろう。逆Y字型の管で液流を増やし目盛りをつけて、計測の相対性を図示するコンセプチュアル仕立てだって可能なのである。このように物象の明確な表層性において、ガラス管と赤い液体、それに環境温度とのあえかな相互関与がたちあらわれる様相は、その同義反復としてみずからを指し示しこそしても意味を代替しているわけではない。
こうしたことに加えて諸泉は、180cmの管を吊って並べること、あるいは管を台つきのケースに納めることなどをとおしても、自己指示としての機能をみたす条件それじたいを明確な形式にしようと慎重に配慮をかさねている。設営空間はといえばそうした配慮がこの空間に規矩をあたえ分節することにもなっている。ジェニー・ホルツァーの電光板によるメッセージをささえる装置の構成体化、あるいはハンス・ハーケのフォトリアリズムになされたことさらな額装や展示の荘厳作為などと同様に、諸泉の設営もひとびとはその十分に吟味された形式をとおしてこそみるのだといってよい。実際に環境温度による赤い計測媒体のかすかなゆらぎとともに時をきざみ全体がたちあらわれるというフレキシブルな設営の構えは、ことほどさように秀逸なのである。
ことがらの指示はことがらの対象化と特定化によっている。そこに意味を内包しない。すでに物質還元された表出は原理上ことがらのメタファではなくことがらの範疇化とその発見へとおもむくだろう。諸泉の手にかかるこれら一種の物体表出についてはむしろこういうべきではあるまいか。かれは未曾有の表出媒体を選び特定してそのありようにはじめてかたちをあたえたのだと。この意想外の媒体は環境ぶくみでそれじたいの構造化とその形式を保有する。かれはそれを十分にみるにあたいするものとして具現させた。
近年にいたり、かれは温度/湿度測定装置によるグラフ、感温液晶でおおわれた柱が示す環境温度による色調変化など新機軸を設営に加えている。しかし、ことの本質がたとえば環境温度をめぐるエコロジー、それにまつわるロマンティックな 想像力一般を肩代わりすることではなく、環境温度と媒体との関与の構造その形式にあるとするなら、これら新機軸はそれはそれとして温度計測管の場合と異質の局面をひらくことになるはずのものである。筆者としては新機軸のそこに興味をつないでゆきたいと思う。
ⒸSHIGERU MOROIZUMI